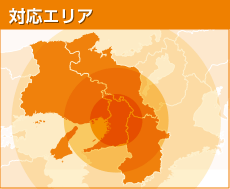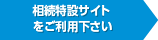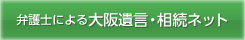共有不動産の賃貸借契約の締結
共有不動産を賃貸する場合、どのようにして決めることができるのでしょうか?
共有不動産の賃貸が、共有物の処分・変更と解されるのなら共有者全員の同意が必要ですが(民法251条)、共有物の管理と解されるのなら持分の過半数により決めることができます(民法252条)。
※「変更」には共有物の物理的変更のほか法律的な処分も含むとするのが通説であり、「管理」とは変更に至らない程度の利用・改良行為を指すとされています。
裁判例では、この点について争われてきましたが、概ね次の結論となっています。
- 民法602条所定の期間内であれば管理行為であり(過半数で決めることができる)、その期間を超える場合は処分・変更に当たる(全員の同意が必要)。
- 民法602条所定の期間を超えない賃貸借であっても、借地借家法の適用を受ける場合には更新を考慮し、原則として処分・変更に当たる(全員の同意が必要)。
ただし、東京地判平成14年11月25日判決・判例時報1816号82頁は、本件ビルは当初から業務用の貸しビルとして建築されたものであることを理由に管理に当たると判断しています。
裁判例
最高裁昭和39年1月23日判決・裁判集民71号275頁
共有土地を賃貸する行為は、民法第252条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」にあたるとされました。
東京地裁昭和39年9月26日判決・判例タイムズ169号194頁
共有に属する物件について民法602条所定の期間を越える賃貸借契約を締結するには、共有者全員の同意を要するものと解すべきである。けだし、右法条の趣旨は、賃貸借の期間があまり長いと実際の利害関係において処分行為に類似してくるところから、一定の期間を定めてそれ以内の賃貸借契約は管理行為とし、それを越えるものを処分行為として、管理の能力乃至権限はあるが、処分の能力乃至権限のないもののなす賃貸借契約について基準を定めんとするにあるが、この趣旨は共有物を第三者に賃貸するという共有者各自の利害を十分に考慮すべき場合に当然推し及ぼさるべく、前記期間を越える賃貸借契約の締結は管理行為ではなくて、処分行為の範疇に属すべきものというべきであるからである。
東京高裁昭和50年9月29日判決・判例時報805号67頁
共有物たる本件土地の賃貸借は、同土地に対するいわゆる管理行為にあたるものと解するのが相当であり、したがって、本件土地賃貸借については、民法第252条の規定によりその共有者の持分の価格の過半数をもって決すべきものといわなければならず、しかもこれによる賃貸借は、処分権限のない者による賃貸借にあたることが明らかであるから同法第602条第2号の規定によりその賃貸期間は5年を超えることが許されないものといわなければならない・・・。
東京地判平成14年11月25日判決・判例時報1816号82頁
原則
一般に、共有物について賃貸借契約を締結する行為は、それが民法602条の期間を超える場合には、共有者による当該目的物の使用、収益等を長期間にわたって制約することとなり、事実上共有物の処分に近い効果をもたらすから、これを有効に行うには共有者全員の合意が必要であると解されるのに対し、同条の期間を超えない場合には、処分の程度に至らず管理行為に該当するものとして、持分価格の過半数をもって決することができるというべきである。しかし、仮に契約上の存続期間が同条の期間を超えないとしても、借地借家法等が適用される賃貸借契約においては、更新が原則とされ事実上契約関係が長期間にわたって継続する蓋然性が高く、したがって、共有者による使用、収益に及ぼす影響は、同条の期間を超える賃貸借契約と同視できると考えられる。したがって、借地借家法等の適用がある賃貸借契約の締結も、原則として、共有者全員の合意なくしては有効に行い得ないというべきである。
これを本件についてみると、本件賃貸借の存続期間は2年間とされているものの、本件賃貸借契約には借地借家法の適用があり、長期間存続する蓋然性が高いから、これを有効に締結するには、本来、共有者全員の合意が必要というべきである。
本件についての検討
しかし、本件における事情にかんがみると、本件賃貸借契約の締結は、管理行為に属するというべきである。その理由は、以下のとおりである。
共有物の変更及び処分に共有者全員の同意が必要とされるのは、これらの行為が共有者の利害関係に与える影響の重大性にかんがみ、これを過半数の持分権者によって決しうるとするのが不相当であるからと解される。したがって、持分権の過半数によって決することが不相当とはいえない事情がある場合には、長期間の賃貸借契約の締結も管理行為にあたると解される。
本件についてみると、(略)によれは、本件ビルは、業務用の貸しビルとして設計され、補助参加人が使用中の本件ビル9階の一部を除く本件ビルのその余の部分を補助参加人が訴外会社に一括して賃貸する形式がとられ、訴外会社がこれを各テナントに転貸して賃料収入を得るという方法で使用されてきたものであること、従来も、本件ビルの各共有権の行使は、ビル運用による収益を分かち合うこと(略)を主目的とし、原告は本件ビルを自己使用するのではなく、訴外会社に賃貸し、賃料収入によって収益を得てきたことが認められ、この点からすれば、原告としても、テナントに賃貸すること以外の使用方法は予定していなかったと推認される。
これを前提とすれば、本件賃貸借契約は、もともと予定されていた本件ビルの使用収益方法の範囲内にあるものということができ、原告(略)及び補助参加人が予定していた本件ビルについての共有権の行使態様を何ら変更するものではない。そして、原告は、自己の持分権に基づき、補助参加人に対する求償権を有すると考えられるから、本件賃貸借契約を有効としても、原告の利益に反するものではない。
このように解した場合、賃借人の選定及び賃料の決定に関して原告の意に添わない賃貸借契約が締結される可能性もあるが、不動産の有効な活用という観点からすれば、賃借人の選定及び賃料の決定は、持分権の過半数によって決すべき事項であると考えられる。
したがって、本件賃貸借契約の締結は管理行為に属するというべきであり、これを行った補助参加人は本件ビルにつき4分の3の持分権を有しているから、本件賃貸借契約は有効に締結されたと認められる。