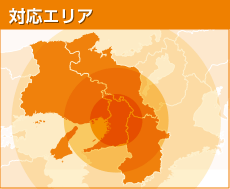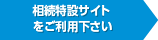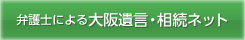境界辺りのブロック塀は誰の所有か?
甲の所有する甲土地と乙の所有する乙土地の境界辺りに設置されているブロック塀等に関連して、次のような紛争が生じることがあります。
- 塀が老朽したため取り壊して、新しい塀を設置したい
- 塀が倒壊しかかっているので、相手方に撤去を請求したい
- 塀が越境しているが、塀は当方が所有しているので越境部分の土地について取得時効を主張したい
このような場合、塀が甲の所有であるのか、乙の所有であるのか、それとも甲と乙の共有であるのかによって結論が変わってきます。
境界辺りに設置されている塀の所有者は誰であるのか、幾つかの裁判例を紹介して説明します。
塀境界線上に存する場合の共有推定
塀が甲土地と乙土地の境界線上に存する場合、当該塀は甲と乙の共有と推定されます(民法229条)。
しかし、あくまで推定されるだけですので、甲もしくは乙の単独所有であることの証拠があれば、それによることになります。
東京地裁昭和50年1月24日判決・下級裁判所民事裁判例集26巻1~4号103頁
同一所有者に属する相隣接する二筆の土地を甲乙両名にそれぞれ譲渡するに際し、その境界線上に設けられ両土地にまたがって存在するブロック塀を甲乙両名に二重に譲渡した場合、同ブロック塀は甲乙の共有となるとされました。
民法229条(境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
乙の単独所有とされた事例
東京地裁平成19年3月28日判決・判例秘書(平成18年(ワ)3267号)
甲土地の所有者が、乙土地の所有者に対し、境界上の塀は甲と乙の共有であると主張して、塀の撤去及び新たに塀を設置することの承諾を求めたものです。判決は、当該塀は乙の所有であるとして甲の請求を棄却しました。
本件囲障が原告と被告らの共有に属するか
⑴ 原告は、本件囲障の一部が原告土地に入り込んでいるものであって、このことからすれば、民法229条により、本件囲障については原告及び被告らの共有と推定される旨主張する。
⑵ しかしながら、本件囲障が原告土地に入り込んでいるといっても、その範囲は地上部分で最大2cmにすぎず、ほとんど測量誤差の範囲にすぎないものであるし、地下についても数十cmとごく僅かな範囲にすぎない。また、前記認定のとおり、本件囲障は、30年以上前に当時被告土地を所有していたA銀行によって設置されたもので、その当時A銀行が設置費用に当たる金員を原告の被相続人又は原告に請求したなどという事情はなく、後記平成12年の境界確認前までは、本件囲障が越境している事実すら認識されたことはなく、その後も、平成17年8月の本件仮処分申立てに至るまでは、何らの紛争もなく推移してきたもので、このことは、本件囲障が被告らのみの共有に属するものであることを強く推認させる。特に、平成12年11月8日の本件境界の確認の結果は、本件囲障がほぼ被告土地内にあることを認めるに等しいものであって、実際に、Bも、本件囲障が被告土地の所有者の所有に属するという認識で、被告らに売却したものであるにもかかわらず、原告が、平成17年8月ころまで本件囲障の所有権の帰属に関して格別異議を唱えたことはなかったことからすれば、原告は、本件囲障につき自己が持分権を有するとの認識をまったく有していなかったことが強く推認される。
さらに、本件囲障は、以前被告土地に建物が存在していたときには、被告所有にかかる西側道路に面した囲障と一体となっていたものであって、これら本件囲障の存続状況・形態は、本件囲障が被告らのみの共有であるとの被告らの主張に沿うものであるといえる(なお、被告土地の東側境界の囲障は東側隣接地所有者の所有として確認されているところ、これは被告土地外に存在するものであり、かつ、被告土地の北側囲障(本件囲障)及び南側囲障と接続されていない。)。
⑶ 以上の事実関係に照らすと、本件囲障に関しては、民法229条の共有推定を覆すに足りる事情が認められるというべきである。したがって、本件囲障は被告らのみの共有に属すると認めるのが相当であって、原告には持分権はないというべきである。
所有権の帰属が不明とされた事例
東京地裁平成25年1月31日判決・判例時報2200号86頁
中古住宅と敷地の売買において、ブロック塀の所有権の帰属の不明であることを理由に、買主が売主に対し、売主の瑕疵担保責任を原因として損害賠償請求した事例において、裁判所は、塀の所有権に帰属が不明であるとしました。尚、本件は、隣接地所有者間の争いではないため、所有権の帰属が不明であること自体が瑕疵に該当するとされたものです。
塀の所有権の帰属の判断について参考となりますのでご参照ください。
判決
(ア) 被告Aらの責任を判断する前提として本件ブロック塀の所有権について検討するに、原告らは、本件ブロック塀は、民法86条1項の土地の定着物であり、不動産の一部として扱われ、建物及び立木以外の定着物はことごとく土地と一体となるから、本件ブロック塀が北側隣地に完全に入り込むことで本件ブロック塀は北側隣地所有者の所有に属することを否定し得ないと主張する。
確かに、本件ブロック塀は囲障であるところ、囲障は、土地に固定的に付着して容易に移動し得ない物であって、取引観念上継続的にその土地に付着した状態で使用されるということはできるから、土地の定着物にあたると解することはできる。
しかしながら、土地の定着物であるとしても、直ちに土地の構成部分となり、いわば土地の所有権に吸収され、常に土地所有者と囲障の所有者が一致するというには飛躍があるように思われる。
被告らが指摘するように、民法229条は、境界線上に設けた囲障について相隣者の共有に属するものと推定しており、相隣者のいずれかの単独所有である場合も想定しているから、少なくとも、境界線上に存する囲障については、土地所有者と囲障の所有者が一致しない部分が出てくるというべきである。そして、ひとたび、単独所有の囲障の一部が境界を超えて別の所有者に属する隣地に完全に入り込んだ場合に、囲障の当該部分が当然に隣地所有者の所有に属することとなるというのは相当でない。また、囲障が越境することによって、越境部分の敷地を時効取得する場合や、土地所有者から越境した囲障の設置者にその撤去が求められる場合があり得ることを考慮すれば、囲障の所有権と土地の所有権が常に一致すると解する必然性はないものと思われる。
確かに、土地の所有者や利用権と無関係に囲障のみを取引の客体として捉える社会的必要性がどの程度あるのかは十分に考慮する必要があるが、少なくとも、隣地の所有者間における囲障の所有権の帰属に関しては、土地所有者と囲障の所有者が異なることが起こりうることを否定できないと解される。
したがって、本件ブロック塀のうち本件境界ブロック塀がD所有の北側隣地に越境している事実のみから、直ちに、本件ブロック塀がD所有に属するということはできない。
(イ) もっとも、別紙図面の本件敷地や北側隣地の地番、形状、道路との位置関係、本件通路部分の共有状態からすれば、本件土地と北側隣地は広大地を小規模宅地に分筆したことにより形成されたものと窺われ、本件敷地と北側隣地の境界も分筆時点において明確であったと推認することができ、囲障を設置する場合には境界がどこであるかを通常は意識するはずであるところ、本件境界ブロック塀が北側隣地に完全に入り込み、しかも、境界に沿っていること、また、本件通路側ブロック塀は、本件通路部分と北側隣地の境界付近に位置しており、北側隣地の囲障となっているとも見れること、さらに、被告Aらにおいて、越境が判明した時点でBと本件ブロック塀の所有関係を確認することができたはずであるのにこれを行っていないことからすれば、北側隣地の所有者が本件ブロック塀を自ら設置し、Dがこれを承継して所有している可能性は否定できない。
他方、被告Aらは、昭和62年にCが本件建物を建築した際に設置したもので被告Aらの所有に属していたと主張している。これを客観的に裏付ける証拠はないが、被告Aらがインターホンや表札を本件通路側ブロック塀に設置して使用してきており、Bから特段の異議を述べられていた形跡もなく、また、本件通路側ブロック塀が本件土地への誘導部分に位置していると見れないわけでもなく、さらに、囲障の設置時に意図せずして越境してしまう可能性が皆無であるとまではいえない上、Dが本件ブロック塀を所有する根拠を具体的に述べているわけでもないから、被告Aらの所有に属し、これが原告らに承継された可能性も否定できない。
(ウ) そうすると、本件ブロック塀がいずれの所有に属するか証拠上必ずしも確定できない状況が生じている。しかも、本件境界ブロック塀が北側隣地に越境していることで、民法229条による推定が働かず、原告らにおいて共有であることの主張が困難になっていることは否定のしようがなく、原告らが共有持分すら有しない場合には、本件ブロック塀をDの承諾なくして利用することは困難であり、たとえ、Bが従前許容していたとしてもDがこれに拘束される根拠がない。逆に、仮に原告らの所有であるとしても、その敷地利用権の立証は容易でないから、Dから撤去を求められる負担を負い、やはり、使用に支障が生じることも考えられる。
さらに、Dが本件ブロック塀の単独所有を主張しており、原告らが本件ブロック塀の共有持分権者と認識していることからすれば、本件ブロック塀の所有権の帰属が不明であり、しかも、本件境界ブロック塀が北側隣地に越境しており、北側隣地所有者との法律関係が不安定になっていることは、否定できず、このような状況にあったこと自体、本件土地建物売買の目的物に瑕疵があるということができる。
(エ) そして、被告Aらにおいても、本件売買契約当時、本件ブロック塀を所有していると認識しており、本件境界ブロック塀が北側隣地に越境していることを知らなかったというのであるから、上記瑕疵は隠れた瑕疵にあたるというべきであり、被告Aらは瑕疵担保責任を免れない。
(弁護士 井上元)